介護職として新しい職場で働き始めたものの、「誰も教えてくれない」「質問しても忙しそうで聞きづらい」といった状況に悩んでいませんか。
新人放置は介護業界で深刻な問題となっており、多くの新人職員が孤立感や不安を抱えながら働いています。
この記事では、介護職の新人放置が起きる原因から具体的な対処法、さらには放置されない職場の見分け方まで、現場経験者の視点から詳しく解説します。
適切な知識と対策を身につけることで、安心して成長できる職場環境を見つけることができるでしょう。
介護職の新人放置とは?現状と悩み

ここでは、まず介護職の新人教育における理想と現実のギャップに焦点を当てます。
本来、新人介護職が安心して成長できるためにどのような教育体制が望ましいのかを示しつつ、実際に多くの職場で「新人放置」という問題がどのように起きているのか、その実態を明らかにします。
本来の新人介護職の教育体制
介護職として働き始める新人の皆さんは、多くの期待と不安を持って入職されると思います。
新人、とはいっても他の施設で働いたことがある場合には、別ですが、全くの介護業界未経験で就職や転職してきた場合などは、人の命にも関わる仕事ですから、大きなプレッシャーもあるでしょう。
そうした不安のある中、安心して業務に取り組めるようになるためには、適切な教育体制が不可欠です。
本来、新人介護職は、先輩職員から丁寧なOJT(On-the-Job Training)を受け、現場で必要な知識や技術を実践的に学ぶことが必要です。
具体的には、ご利用者の身体介護の方法、コミュニケーションの取り方、緊急時の対応、記録の書き方など、多岐にわたるスキルを段階的に習得していく必要があります。
また、新人の皆さんの成長をサポートするために、専任の教育担当者がつき、定期的なフィードバックや面談の機会が設けられることが理想的です。
分からないことや不安なことを相談しやすい環境は、新人介護職の心理的な負担を軽減し、自信を持って業務に臨むための土台となるものです。
離職を防ぎ、安全で質の高い介護を提供するためには、新人職員に対しての教育体制はとても大切です。
新人放置が起きている職場の実態
しかし、残念ながら介護現場の中には、本来あるべき新人教育が十分に機能していない「新人放置」が起きている現場もあります。
新人放置とは、具体的に以下のような状況を指します。
- 業務内容や手順について、具体的な説明がないまま現場に立つことを求められる。
- 質問しにくい雰囲気があり、困っていても誰にも聞けない。
- 入職して間もないにもかかわらず、一人で責任の重い業務を任される。
- 困っているように見えても、先輩職員から声をかけてもらえない。
- 他の職員が忙しそうで、話しかけるタイミングがない。
このような状況では、新人の皆さんは大きな孤独感や不安感を抱えやすくなります。
自分の役割が分からず、何をすれば良いのか迷ってしまうことも少なくありません。
結果として、業務のミスが増えたり、自信をなくしたり、精神的・肉体的に疲弊して体調を崩してしまうことさえあります。
これは、新人職員が成長できなくするだけではなく、利用者さんへの介護の質にも影響を及ぼしかねない深刻な問題です。また、短期離職といった問題にもつながるでしょう。
新人放置がもたらす影響と短期離職の関係
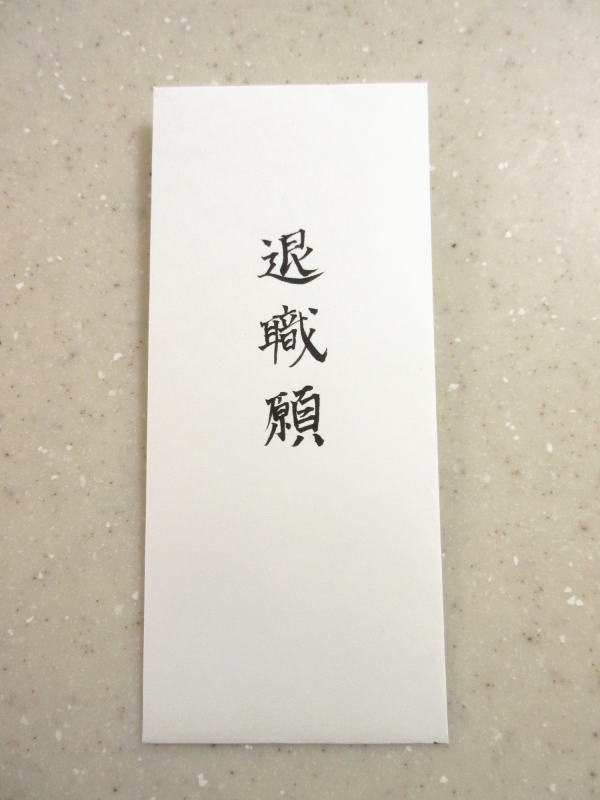
新人放置は単なる教育不足にとどまらず、職員の心身に深刻な影響を与え、最終的には短期離職という結果を招いてしまうこともあります。
適切な指導を受けられない新人職員は、技術的な不安だけでなく精神的な負担も抱えることになり、介護職としてのキャリアを諦めてしまうケースも少なくありません。
ここでは、新人放置が職員に与える具体的な影響と、それが短期離職につながる理由についてまとめたいと思います。
もしかすると、以下のような悩みを抱えている介護職の方も多いかもしれません。
この章の後、対処法なども解説していきます。
新人職員が感じるストレスや不安

放置された新人介護職員は、まず技術面での大きな不安を抱えることが多いでしょう。
専門的な知識や技術がまだ身についていない段階で、十分な説明もないまま業務を任されることは、大きなプレッシャーです。
特に、利用者さんの身体に触れる介護業務では、「もしミスをしてしまったらどうしよう」「利用者さんに怪我をさせてしまったら」という強い恐怖心がつきまといます。
また、利用者の急変時や緊急事態への対応方法が分からず、「何かあったらどうしよう」という責任の重さに押し潰されそうになることもあります。
人間関係においても、質問しても冷たくあしらわれたり、「そんなことも分からないの?」と言われたりすることで、職場での孤立感を深めていきます。
このような状況が続くと、仕事に行くこと自体が苦痛になり、不眠や食欲不振などの身体症状まで現れてしまう、といったケースもあります。
職場環境によるモチベーション低下
新人放置が起きる職場では、職員同士のコミュニケーションが不足していることが多く、チームワークの欠如が新人職員のモチベーション低下を招きます。
「介護の仕事を通じて利用者の役に立ちたい」という理想や気持ちを持って入職したにも関わらず、適切な指導を受けられないことで成長実感を得られません。
先輩職員からの承認や評価もなく、自分の仕事ぶりが正しいのか判断できないまま日々を過ごすことになります。
また、職場の雰囲気に馴染めず、人間関係の構築に悩むことも少なくありません。介護の仕事はチームで行うものですから、円滑な人間関係は業務をスムーズに進める上で非常に重要です。
孤立した状況が続けば、仕事へのやりがいを見失い、「この仕事は自分には合わないのではないか」といったネガティブな感情を抱きやすくなります。結果として、介護職そのものに対する興味や情熱が薄れてしまうことにも繋がりかねません。
短期離職が発生する具体的な要因
介護労働安定センターが公表した、2023年度介護労働実態調査の結果によると、介護職の離職率は、13.1%でした。
参照:令和5年度「介護労働実態調査」結果の概要について
また、1年以内に辞めた人の割合は以下のような調査結果もあります。
一方、調査対象期間に採用した介護職員のうち、すでに離職した人(新規採用後 1年以内に辞めた人)は全体で 19.6%と、訪問介護員よりも高くなっている。
引用:介護労働安定センター 令和5年度介護労働実態調査事業所における介護労働実態調査 結果報告書 P.31
放置によって蓄積されたストレスや不安が限界に達すると、新人職員は「もうこの職場では働き続けられない」と感じ、早期の退職を決断する傾向にあります。
- 成長機会の欠如: 適切な教育を受けられないことで、スキルアップやキャリア形成の見通しが立たず、この職場では自分の成長が望めないと感じる。
- 孤立感と不信感: 誰にも相談できず孤立した状況が続くと、職場への不信感が募り、帰属意識が低下する。
- 心身の疲弊: 常に不安やストレスに晒されることで、心身ともに疲弊し、これ以上働き続けることができないと判断する。
- 他職場への期待: 介護業界全体で人手不足が続く中で、より良い教育体制や働きやすい環境を求めて、他の介護施設への転職を検討し始める。
このように、新人放置は単に業務を覚えられないという問題に留まらず、新人の皆さんが安心して働き続けることを困難にし、最終的には貴重な人材の流出に繋がってしまうことになります。
介護職で新人放置が起きる理由

この章では、なぜ新人介護職が放置されてしまうのか、主となる原因を以下にご紹介します。
表面的な問題だけでなく、介護業界全体が抱える構造的な課題から、個々の職場や職員に起因する問題まで、具体的な背景があります。
職場として改善が難しい可能性もあり、そうした場合には、職場を変えるなどの根本的な対策が必要になることもあります。
人手不足で教育担当者を確保できない
介護業界全体が慢性的な人手不足に陥っていることは、新人放置の大きな要因の一つです。
多くの施設で、ギリギリの人数で業務を回しているため、新人の教育に十分な時間や人員を割くことが難しいのが現状です。
経験豊富なベテラン職員も常に業務に追われており、新人に指導する余裕がない場合があります。
また、そもそも教育担当者という役割を設けていない、あるいは設けていても本来の業務と兼任しているため、新人に手厚い指導ができないケースも少なくありません。
教育担当者が不在であったり、複数人の新人を同時に担当していたりすると、一人ひとりに目が行き届かず、結果的に放置に近い状態になってしまいます。
業務が忙しく指導時間を確保できない
介護現場は常に多忙であり、一日の業務スケジュールが分刻みで組まれていることも珍しくありません。
利用者さんのケア、記録業務、申し送り、緊急時の対応など、目の前の業務をこなすことに精一杯で、新人に丁寧に指導する時間を確保できないという問題があります。
特に、急な体調変化や転倒など、予測できない事態が発生した際には、ベテラン職員がその対応に追われ、新人の指導が後回しになってしまうこともあります。
このような状況が続くと、新人は質問するタイミングを失い、分からないことがあっても「忙しそうだから聞けない」と遠慮してしまい、結果的に放置されていると感じてしまうのです。
教育制度やマニュアルが整備されていない
新人教育を効果的に行うためには、しっかりとした教育制度やマニュアルが不可欠です。
しかし、一部の介護施設では、新人教育のための具体的なカリキュラムやOJTマニュアルが存在しない、あるいは形骸化していることがあります。
教育内容が属人化しており、新人の指導が特定の職員の経験や判断に委ねられている場合、指導の質にばらつきが生じやすくなります。
新人に何を教え、どこまで業務を任せるかという共通認識がない職場全体に無い状態では、教育は難しいです。
このような状況では、新人は何をどのように学べば良いのか分からず、自ら積極的に動こうとしても限界が生じてしまいます。
職員同士の連携が取れていない
介護の仕事はチームプレイであり、職員同士の密な連携が重要です。しかし、職場内のコミュニケーションが不足していると、新人に関する情報共有がスムーズに行われず、放置に繋がることがあります。
例えば、新人の現在の習熟度や苦手なこと、困っていることなどが職員間で共有されていないと、それぞれの職員が「誰かが教えているだろう」と考えてしまい、結果的に誰も新人の状況を把握していないという事態が生じます。
また、特定の職員にばかり新人指導の負担が集中してしまい、その職員が不在の際に新人が孤立するといった問題も発生しやすくなります。
新人職員への無関心やいじめ・ハラスメント
残念ながら、一部の職場では、新人職員への無関心や、さらにはいじめ・ハラスメントが新人放置の背景にあるケースも存在します。
新人のことを気にかけず、困っている様子を見て見ぬふりをする職員がいると、新人はますます孤立し、質問することもためらうようになります。
また、言葉による精神的なプレッシャーや、故意に業務を教えないといったハラスメント行為が、新人を追い詰めることもあります。
このような職場環境では、新人は安心して働くことができず、精神的な負担も大きくなるため、早期の離職に繋がりやすくなります。
職場の文化や人間関係が、新人教育の質に大きく影響していると言えるでしょう。
新人介護職が放置されたと感じた時の具体的な対処法

ここでは、もし新人介護職が「放置されている」と感じた時に、状況を改善するために具体的にどのような行動を取るべきか、対処法を解説します。
大切なのは一人で抱え込まないことです。
例えば、上司にも放置されている…と思っていたとしても、上司も忙しすぎて気が回っていなかっただけ、といったことも話してみると分かるケースがあります。
その後、しっかりサポートしてもらえる状態になる、といったこともありますので、まずは話してみること。こうした行動を大切にしてみていただけたらと思います。
まずは自己判断せず、状況を整理する
放置されていると感じた時、まずは冷静に状況を整理することが大切です。
感情的になる前に、本当に放置されているのか、それとも自身の理解不足や思い込みではないか、客観的に見つめ直してみましょう。例えば、「いつ」「誰に」「どのような状況で」放置されたと感じたのかを具体的にメモに取ることをおすすめします。
この時、事実に基づいて記録することが重要です。
例えば、「〇月〇日の〇時頃、〇〇さんが私に業務を教えずに、別の職員に指示を出していた」といったように、具体的な行動を記録することで、後で誰かに相談する際にも状況を正確に伝えられます。
自己判断だけで悩みを深めるのではなく、具体的な状況を把握することで、次の行動に移りやすくなります。
この段階で重要なのは、「自分に問題があるのではないか」と自分を責めすぎないことです。
新人教育は職場の責任であり、適切な指導を受けられないのは個人の能力の問題ではありません。
積極的に質問・相談する際のポイント
放置されていると感じる状況でも、自ら積極的に質問や相談を試みることは非常に重要です。
ただし、やみくもに質問するのではなく、いくつかのポイントを押さえることで、より効果的に情報を引き出せます。
- タイミングを見計らう: 先輩職員が比較的落ち着いている時間帯や、手が空いていそうな時に声をかけるようにしましょう。
- 具体的に質問する: 「何も分かりません」ではなく、「〇〇の業務で△△の部分が分からず困っています。どのようにすれば良いでしょうか?」と具体的に質問内容を伝えることで、相手も答えやすくなります。
- メモを取りながら聞く: 教えてもらったことはその場でメモを取り、同じことを何度も質問しないよう努めましょう。
- 相手の状況を察する: 忙しそうであれば、「今、少しお時間よろしいでしょうか?」と尋ね、相手の状況を配慮する姿勢を見せることも大切です。
教えてもらったことはメモを取り、後で確認できるようにしておくことで、同じ質問を繰り返さないよう注意しましょう。
もし質問しても教えてもらえない、あるいは冷たくあしらわれる場合は、次のステップとして、別の方法を考える必要があるかもしれません。
信頼できる先輩職員や同期に相談する
職場の中に、比較的親身になってくれる先輩職員や、同期がいる場合は、積極的に相談してみましょう。
彼らはあなたの気持ちに共感してくれるだけでなく、職場の内部事情や、新人が抱えがちな問題について理解があるため、具体的なアドバイスをしてくれるかもしれません。
先輩職員からは、過去の経験に基づいた実践的な対処法や、職場の暗黙のルール、質問しやすい職員の見分け方などを教えてもらえる可能性があります。
また、同期に相談することで、「自分だけじゃないんだ」という安心感を得られ、精神的な負担が軽減されることも少なくありません。
一人で抱え込まず、頼れる存在を見つけることが、状況を改善するための第一歩となります。
上司や管理職に現状を伝える
信頼できる先輩や同期に相談しても状況が改善しない場合、あるいは深刻な放置状態が続く場合は、上司や管理職に直接現状を伝えることも検討しましょう。
この際も、感情的にならず、前述のように具体的にメモを取った事実に基づいて冷静に説明することが重要です。
例えば、「〇月〇日の〇〇の業務で、△△について教えていただけず困っています。このままでは利用者様の安全にも影響が出るのではないかと不安です」といったように、業務上の問題として提起する形であれば、上司も真剣に受け止めてくれる可能性が高まります。
相談しても改善が見られない場合は、さらに上の役職者や、施設の相談窓口などに次のステップとして働きかけることも視野に入れましょう。
地域の相談窓口やハローワークを利用する
職場内で問題を解決することが難しいと感じた場合は、外部の相談窓口を利用することも有効な手段です。
例えば、労働基準監督署や、都道府県の労働局では、労働に関する様々な相談を受け付けています。ハラスメントや不適切な労働環境に関する相談も可能です。
また、ハローワークの職業相談窓口では、個別の職業相談に応じてくれるだけでなく、場合によっては、労働問題に関する専門機関への案内もしてくれます。
匿名での相談が可能な窓口もあるため、まずは情報収集のために利用してみるのも良いでしょう。専門家からの客観的なアドバイスや、転職支援などの情報が得られることで、今後の選択肢が広がるかもしれません。
新人教育が充実した職場を選ぶポイント

新人放置の問題を根本的に解決するためには、就職・転職の段階で適切な職場を選ぶことが最も重要です。
事前の情報収集と慎重な職場選びにより、新人教育が充実した環境で安心してキャリアをスタートすることができます。
ここでは、新人放置が起きにくい職場を見極めるための具体的な方法を解説します。
教育制度の確認方法
新人教育が充実している職場を見つけるためには、まずその施設の教育制度を具体的に確認することが重要です。
単に「研修制度あり」と書かれているだけでなく、以下のような点が明確になっているかを確認しましょう。
- 体系的な研修プログラムの有無: 入職時研修はもちろんのこと、定期的なスキルアップ研修や、ご利用者の状態に応じた専門的な研修が用意されているか。段階的にスキルを習得できるようなプログラムがあるかどうかがポイントです。
- OJT制度の明確さ: OJT(On-the-Job Training)の担当者が固定されているか、OJTの期間や目標が具体的に設定されているかを確認しましょう。OJT担当者が明確であれば、誰に質問すれば良いか迷うことも減ります。
- eラーニングや座学研修の有無: 現場でのOJTだけでなく、座学やeラーニングシステムを活用して、介護の知識や技術を理論的に学ぶ機会が提供されているかどうかも重要です。
- 資格取得支援制度: 介護福祉士などの専門資格取得に向けた支援(費用補助や勤務時間の調整など)がある施設は、職員の育成に積極的であると判断できます。
職場見学で注目すべき点
職場見学は、実際に働く環境を肌で感じられる貴重な機会です。
単に施設を見るだけでなく、新人教育の充実度を測るための具体的な視点を持って臨みましょう。
- 職員同士のコミュニケーション: 職員間で気軽に声かけが行われているか、新人が質問しやすい雰囲気があるか、笑顔が多いかなどを観察します。活発なコミュニケーションが見られれば、困った時に助け合える環境である可能性が高いです。
- 業務中の指導状況: 先輩職員が新人に具体的に指導している場面があるか、一方的に指示を出すだけでなく、その理由や背景まで説明しているかを確認します。
- 情報共有の仕組み: 朝礼や申し送り、カンファレンスなどが定期的に行われ、職員間で利用者さんに関する情報や業務の進捗が円滑に共有されているかを見ます。情報共有がしっかりしていれば、新人も状況を把握しやすくなります。
- 休憩室の雰囲気: 休憩中の職員の様子が和やかか、新人職員も他の職員と打ち解けて会話しているかなど、休憩時間の過ごし方にも注目してみましょう。
- 整理整頓された環境: 職場全体が整理整頓されており、マニュアルや資料がすぐに手に取れる場所に置かれているかなども、業務の効率性や教育体制の整い具合を示す間接的な指標となります。
面接で質問すべき内容
面接では、入社後の具体的な働き方や教育について、積極的に質問しましょう。
以下のような質問は、新人教育に関する施設の考え方や体制を深く知るために役立ちます。
- 「入職後、最初の1ヶ月でどのような業務を任されますか?」
- 「新人教育の担当者はどなたになりますか?その方はどのような役割を担いますか?」
- 「研修期間中、定期的に面談などは行われますか?フィードバックの機会はありますか?」
- 「困ったことや分からないことがあった場合、どのようにサポートしていただけますか?」
- 「貴施設(事業所)の新人定着率はどのくらいですか?」
- 「貴施設(事業所)の教育理念や方針について教えてください。」
これらの質問に対する相手の答え方や、具体的な説明の有無から、その施設が新人教育にどれだけ力を入れているかを見極めることができます。
まとめ|新人介護職が安心して働ける介護現場を選ぶために
新人介護職にとって、職場での「放置」は、ただ業務を覚えられないというだけでなく、大きな精神的負担や不安に繋がり、最終的には早期の離職を招く深刻な問題です。
実際、放置(に近い状況も含め)になってしまっている新人介護職の方は深く悩んでいるのではないでしょうか。
介護の仕事は、ご利用者の生活を支える重要な役割を担っており、そのためには新人の皆さんが安心して学び、成長できる環境が何よりも大切です。
この記事では、新人放置がなぜ介護現場で起こるのか、その背景にある人手不足や教育体制の不備といった構造的な問題から、実際に放置されたと感じた時の具体的な対処法、そして何より、そうした状況を避けるために良い職場をどのように見極めるかについて解説してきました。
もしあなたが現在、新人放置に悩んでいるのであれば、一人で抱え込まず、今回ご紹介した「質問・相談のポイント」や「外部の相談窓口の利用」などを参考に、行動してみることも考えてみてください。
そして、これから介護職を目指す方や、より良い職場への転職を考えている方は、求人情報の見方、施設見学での観察ポイント、面接での質問内容、転職エージェントの活用など、具体的な「職場選びのポイント」をぜひ実践してみてください。
介護職は、利用者さんの笑顔に直接触れ、感謝されることの多い、非常にやりがいのある仕事です。
このやりがいを長く感じながら、介護のプロとして成長していくためには、適切な教育とサポートが受けられる職場を選ぶことが不可欠です。
この記事が、皆さんが安心して働ける介護現場を見つけ、介護職としてのキャリアを長く安定して築いていくヒントになりましたらとても嬉しいです。